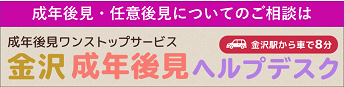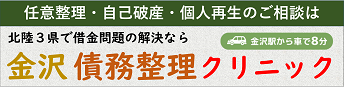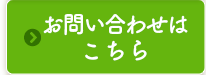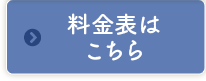相続不動産の売却について
○相続不動産の売却準備
1.遺産分割協議と相続登記の申請
相続した不動産を売却するためには、まず、その不動産の名義を亡くなった人(被相続人)から相続人名義に変更する手続き(相続登記)が必要となります。ここで問題となるのが、誰の名義にするかです。
相続人が一人しかいなければ、その相続人が相続放棄をしない限り、必然的にその相続人名義にすることになります。また、被相続人が生前に遺言をしていて、その遺言で不動産の相続人や受遺者を指定していた場合は、原則としてその内容に従います。
被相続人が遺言をしておらず、相続人が複数いる場合は、
(1)遺産分割協議を行った上で、特定の相続人の単独名義にしてから売却する。売買代金は、その相続人が全額を取得する。
(2)遺産分割協議を行った上で、特定の相続人の単独名義にしてから売却する。ただし、売買代金は複数の相続人で分配する。
(3)遺産分割協議を行った上で、複数の相続人の共有名義にしてから売却する。売買代金は共有持分に応じて複数の相続人で分配する。
(4)遺産分割協議を行わずに、法定相続分に従った共有名義にしてから売却する。売買代金も法定相続分に従って各相続人が取得する。
などの方法が考えられます。
上記のうち(1)の方法は、例えば、相続人が被相続人の長男と二男の2名で、長男が時価1000万円相当の自宅を単独で相続してから売却し、代金を取得する一方で、二男は額面1000万円の預貯金を相続するといった場合です。ただし、不動産を相続してから売却する場合は、相続登記の費用(登録免許税と司法書士への報酬)や、自宅内部の残置物の片付け費用、不動産売却のための宅建業者への仲介手数料の支払いのほか、売買代金に対して後述する譲渡所得税が課税される可能性もあります。そのため、これらの費用も考慮したうえで遺産分割協議をしないと、遺産の分配が実質的には不公平になってしまうこともあります。
(2)の方法は、例えば、相続人が被相続人の長男と二男と長女の3名で、不動産も預貯金もいったんは長男がすべて相続するものの、二男や長女には、ある程度の(例えば法定相続分に応じた)代償金を分配するという方法です。この方法のメリットは、不動産や預貯金をいったんは長男が単独で取得するため、その内容で遺産分割協議書を作成してしまえば、その後の不動産の相続登記や売却手続き、預貯金の解約手続きを長男の印鑑だけで行えることです。ただし、デメリットとしては、不動産の売却価格が決まらないと、二男や長女に渡す代償金の金額を決めづらいことや、前述の相続登記の費用、片付け費用、仲介手数料などをきちんと計算しておかないと、長男が実質的に相続する金額が予想外に低く(高く)なってしまったりする場合がある事です。また、不動産売却に際して譲渡所得税がかかる場合は長男のみが確定申告をすることになりますが、この税金分も考慮する必要がありますし、長男が自営業者で国民健康保険に加入している場合、国民健康保険料は前年の所得に応じて計算されるため、不動産譲渡所得が発生すると連動して翌年の保険料も増加しますので、それも考慮しないと、長男だけが実質的に損をしてしまうといったことにもなりかねません。そのため、この方法を採用する場合は、代償金の金額の算定については税理士等の専門家に相談することをお勧めします。
(3)の方法は、例えば、相続人が被相続人の長男と二男と長女の3名で、不動産については各3分の1の持分での共有として、とりあえず相続登記をしてしまう方法です。なお、遺産分割協議を行いますので、この割合は必ずしも法定相続分のとおりにしなければならないわけではなく、特別受益や寄与分などを考慮して、例えば長男が2分の1、二男と長女が4分の1といった具合に変えることもできます。この方法のメリットは、とりあえず遺産分割の結果が登記記録上に反映されるので、権利関係が明確になります。また、不動産の立地条件が悪いなどの理由によって売却に時間がかかりそうだが、相続税の申告期限までには遺産分割を終了させておきたいような場合もあります。なお、相続登記の費用、片付け費用、仲介手数料は持分の割合に応じて各相続人が負担し、譲渡所得税はそれぞれの相続人が確定申告を行って納税することになります。ただし、デメリットとしては、不動産を売却する際の売買契約や代金決済の際には、その不動産の共有者である相続人全員の出席を求められたり、契約書や委任状に全員の印鑑を押したりしなければならないことなどがあります。
(4)の方法は、例えば、遺産相続を巡って相続人同士の意見が対立し、遺産分割がまとまらない場合などに行われるものです。相続登記は、相続人全員が実印を押印した遺産分割協議書を添付しなくても、民法で定められた法定相続分に従った共有にする場合であれば、相続人のうちの1人からでも申請できます。その際に、他の相続人の同意は必要ありません。しかしながら、そもそも相続人同士の意見が対立している状況では、共有名義にした不動産を売却する際にも、どの仲介業者(買取業者)に依頼するのか、売却価格はいくらにするのかなどについても、意見が合わない可能性があります。ちなみに、このような場合、不動産全体ではなく、自分の持分だけを売却することも可能です。法的にも問題ありませんし、持分のみを買い取る専門業者もあるようです。ただし、一般に、そのような場合は買取価格は相場よりも低くなることが多いでしょうし、勝手に自分の持分だけを売却したことで相続人同士の人間関係がさらに悪化する危険性もあります。
また、上記以外に、とりあえず、相続人全員の同意のもとで、相続不動産の売却を仲介業者に依頼してみて(あるいは買取業者に打診してみて)、売却条件などが判明してから遺産分割協議を行って、名義をどうするか(相続人代表者の単独名義にするか複数の相続人の共有名義にするか)や代金の分配をどうするかを考えるという方法もあります。この場合でも相続登記は済ませる必要はありますが、それを売買が決まるまでは引っ張るという考え方です。ただし、遺産総額から相続税の申告が必要な場合は、申告期限までには遺産分割を済ませないと各種の特例を使えなくなる可能性があるので、注意が必要です。
2.抵当権等の抹消申請
売却予定の不動産に抵当権や根抵当権などの担保権がついている場合、通常はその担保権を抹消しておかないと買い手がつかないため、実質的に売却ができないことになります。
相続不動産に抵当権がついている場合、まず、その抵当権に関する債務(金融機関等からの借金)が完済されているか否かを、その金融機関等に確認する必要があります。なお、抵当権が、被相続人がその不動産を購入したり新築したりした際の住宅ローンに関するものである場合は、残債は「団体信用生命保険(団信)」によって完済されることが多いので、それも含めて確認します。
債務は完済されているが抵当権は抹消されずに残っている場合は、金融機関に「弁済証書」や「抵当権の解除証書」(名称は金融機関によって異なります)、「抵当権抹消の委任状」、「抵当権設定契約書(抵当権の登記済証)」や「抵当権の登記識別情報」を交付してもらいます。なお、債務を完済したのが過去のことですでに交付済みといわれたら、自宅内などに残っていないかを確認し、見つからない場合は「抵当権の解除証書」や「抵当権抹消の委任状」を金融機関等に再発行してもらいます。これらの書類を司法書士に渡して、抵当権抹消登記を申請してもらいます。なお、抵当権抹消登記を申請するには、前提として所有権移転登記(相続登記)が必要となりますので、それも合わせて司法書士に依頼します。
なお、抵当権ではなく根抵当権が設定されている場合、根抵当権は債務を完済したからといって、必ず解除してもらえるというものではありませんが、残債がない場合は解除してくれることが多いと思いますので、根抵当権者である金融機関等に相談することになります。
債務が完済されていない場合、通常は残債を完済しない限り、金融機関等は抵当権や根抵当権の抹消には応じないことが多いと思いますが、その不動産を売却した代金で債務を返済する場合は、金融機関等にその旨を告げて交渉することになります。
○相続不動産の売却代金にかかる税金について
1.譲渡所得税の概要
相続不動産の売却代金は「譲渡所得税」の課税対象となり、所得税と住民税が課税されることがあります。課税されるかされないかは、その不動産について「売却益」が出ているかどうかで決まります。
まずは大雑把に説明すると、例えば、父親が20年前に2000万円で購入した土地を相続してから1500万円で売却した場合は500万円の「売却損」となるので譲渡所得税は課税されませんが、2500万円で売却した場合は500万円の「売却益」が出るので、その500万円に対して20%(所得税が15%、住民税が5%)の譲渡所得税が課税されます(もっとも、後述するように、実際には仲介手数料や印紙代なども売却益から差し引くことができます)。
ただし、建物については所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。そのため、父親が20年前に1500万円で新築した建物を相続してから1000万円で売却したので、500万円の売却損だから譲渡所得税は課税されないとは言い切れません。
譲渡所得は、事業所得や給与所得などの所得とは別々に計算することになっています(分離課税)。
譲渡所得は、所有期間によって長期譲渡所得と短期譲渡所得の二つに区分され、税金の計算も別々に行います。
・長期譲渡所得:譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるものをいいます。
・短期譲渡所得:譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下のものをいいます。
(詳細は国税庁のウェブサイトでご確認ください)
上記で「所有期間」とは、土地や建物を取得した日から、売却した年の1月1日までの期間で計算します。なお、相続した土地や建物を売却する場合、取得した日は相続人がその土地や建物を被相続人から相続した日(=被相続人の死亡日)からではなく、被相続人がその土地や建物を取得した日(例えば被相続人がその土地や建物を購入した日)から計算することになっています。要するに、親から相続した土地や建物であれば、親の所有期間を引き継げるということです(国税庁のウェブサイトより)。
また、贈与によって土地や建物を取得した場合も、贈与者(あげた人)の取得の時期が受贈者(もらった人)に引き継がれます。つまり、親子間贈与や夫婦間贈与があった場合も、所有期間は通算できるということです。
2.長期譲渡所得の税額の計算方法
譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える土地や建物を売ったときの税額の計算は、次のようになります(国税庁のウェブサイトより)。
・所得税額={譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除}×15%
※平成25年から令和19年までは復興特別所得税として、上記所得税額の2.1%が加算されます。
・住民税額={譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除}×5%
3.短期譲渡所得の税額の計算方法
譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以下の土地や建物を売ったときの税額の計算は、次のようになります(国税庁のウェブサイトより)。
・所得税額={譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除}×30%
※平成25年から令和19年までは復興特別所得税として、上記所得税額の2.1%が加算されます。
・住民税額={譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除}×9%
4.譲渡価額とは
譲渡価額とは、土地や建物を売却した金額です。
5.取得費とは
(1)取得費に含まれるもの
取得費とは、今回売却した土地や建物を被相続人が昔購入したときの代金や、当時新築したのであれば建設代金、購入時に支払った仲介手数料や登記費用、印紙代など、その土地や建物の取得に要した金額に、その後支出した設備費や改良(リフォーム)費などの金額を加えた合計額をいいます(詳細は国税庁のウェブサイトに掲載)。
なお、建物の取得費は、購入代金又は建築代金などの合計額から所有期間中の減価償却費相当額を差し引いた金額となります。
(2)相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
相続又は遺贈により取得した土地や建物を一定期間内に譲渡した場合は、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができます。「相続不動産は3年10か月以内に売却した方が良い」という話を聞いたことがあるかもしれませんが、この特例のことで、相続税の申告期限から3年以内に相続不動産を売却すれば、譲渡所得税が軽くなるというものです。相続税の申告期限は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内なので、合計の期間は3年10か月となります(適用要件については国税庁のウェブサイトをご確認ください)。
(3)取得費が不明な場合(概算取得費)
ここでよく問題になるのが、取得費が不明の場合です。相続人にとっては自分が購入した土地や建物ならともかく、自分が子供の頃に親が買った土地や建物の取得費など、わからないことの方が多いと思います。このような場合に、親が土地を買ったり建物を建てた当時の売買契約書や工事請負契約書、代金や仲介手数料の領収書、リフォーム時の費用の分かる資料などが残っていれば、それをもとに取得費を計算することができます。ところが、こうした資料がない場合は、取得費はどのように計算すればいいのかですが、国税庁のウェブサイトには、次のように記載されています。
「売った土地建物が先祖伝来のものであるとか、買い入れた時期が古いなどのため取得費が分からない場合には、売った金額の5%相当額を取得費とすることができます。」
つまり、今回親から相続した土地と建物を1000万円で売却した場合、そのうちの5%(50万円)は、取得費として「認めてあげましょう」とのことです。たったの5%です。ということは、上記の計算式で、長期譲渡所得の場合、譲渡費用が50万円、特別控除がないとすると、
・所得税額={1000万円-(50万円+50万円)}×15%=135万円
・住民税額={1000万円-(50万円+50万円)}×5%=45万円
→なんと、合計で180万円もの税金がかかってしまうことになります。
しかし、考えてみれば、日本の土地の価額は、バブル経済の時期を頂点として、その後は一部の地域を除き、おおむね下落傾向にあります。また、建物(とくに木造家屋)の場合は、築数十年もすれば売却価格はゼロに等しく、場合によっては解体費用が土地値から差し引かれる場合もあります。そうすると、建物の減価償却費相当額を考慮したとしても、親が土地や建物を取得した時の代金や諸費用の合計額よりも、今回の売買代金の方が高額であるなどとということは、少ないのではないでしょうか。そして、もしそのことを示す証拠資料が見つかれば、譲渡益はゼロ(むしろ譲渡損となる)になるため、上記の税金もゼロになる可能性があります。
なお、取得費が不明の場合でも、一般財団法人日本不動産研究所から出されている「市街地価格指数」を用いて取得費を算出するなど、合理的な算出方法により取得費を算定できる場合は、そちらの金額を用いて税額を計算することもできるようですが、かなりの専門知識に基づいて理論武装をしないと税務署から難癖をつけられたときに対応できない可能性がありますので、そのような場合は専門家に依頼することをお勧めします。
いずれにしても、相続不動産を売却する際には、まずは被相続人がその土地や建物を取得した際の費用がわかる書類がないかどうかを、入念に探してみる必要があります。また、自分が土地や建物を購入した際には、売買契約書など取得費の分かる資料は、必ず保管しておくことをお勧めします。
6.譲渡費用とは
譲渡費用とは、相続した土地や建物を売るために支出した費用のことで、仲介手数料、測量費、売買契約書の印紙代、売却するときに借家人などに支払った立退料、建物を取り壊して土地を売るときの取壊し費用などです(詳細は国税庁のウェブサイトに掲載)。
なお、相続不動産を譲渡する際には前提として相続登記が必要ですが、相続登記の費用は譲渡費用には含まれません。ただし、前述の取得費に含めて計算することができます(国税庁のウェブサイトより)。
7.特別控除とは
(1)空き家に係る特別控除の特例
相続又は遺贈によって取得した被相続人居住用家屋やその敷地等を、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。これを、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例といいます。
特例の対象となる「被相続人居住用家屋」とは、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋で、次の3つの要件全てに当てはまるもの(主として被相続人の居住の用に供されていた一の建築物に限ります。)をいいます。
イ 昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
ロ 区分所有建物登記がされている建物でないこと。
ハ 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。
また、特例の対象となる「被相続人居住用家屋の敷地等」とは、相続の開始の直前において被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地又はその土地の上に存する権利をいいます。
この特例を受けるためには、相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ることなど、様々な適用要件があります、詳細については国税庁のウェブサイトでご確認ください。この特例を受けるためには、税務署に確定申告をすることが必要です。
(2)居住用財産の特別控除の特例
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。これを「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といいます。
この特例は(被相続人ではなく)相続人が、売却する相続不動産を自宅として居住していた場合に受けられるものです。例えば、夫婦でマンションに住んでいて夫が亡くなり妻が相続した場合や、親子で一戸建てに住んでいて、親が亡くなり子が相続した場合などが対象となります。
なお、特例を受けるための適用要件については、国税庁のウェブサイトでご確認ください。この特例を受けるためには、税務署に確定申告をすることが必要です。
8.確定申告について
不動産の譲渡所得が発生する場合は、確定申告が必要となります。具体的には、
・譲渡価額-(取得費+譲渡費用)の計算結果がマイナスになる場合(譲渡損となる場合):確定申告は不要
・譲渡価額-(取得費+譲渡費用)の計算結果がプラスになる場合 (譲渡益がある場合):確定申告が必要
となります。なお、譲渡益はあるが特別控除を受ければ計算上が納税は不要となる場合でも、特別控除(後述)の適用を受けるためには確定申告が必要となりますので、注意が必要です。
確定申告は、相続不動産を売却した年の翌年の2月16日~3月15日の間に行います(ただし、新型コロナウィルス感染拡大の関係で、令和2年と令和3年は4月15日まで延長されていました)。
9.健康保険料等への影響
不動産を売却により譲渡所得が発生すると、健康保険料に影響が生じることがあります。前述のように、譲渡所得は給与所得や事業所得とは別の分離課税が適用されます。そのため、会社員の方が加入している健康保険(協会けんぽ・組合健保)や、公務員や社会福祉法人の方が加入している共済保険については、標準報酬月額と呼ばれる会社等から支払われる給与が基準となっているため、譲渡所得が発生しても保険料には影響しません。ただし、被扶養者について譲渡所得が発生した場合、年収130万円を超えることになるため、保険組合によっては扶養から外れてしまう可能性があります。そのため、保険組合へ事前に確認することをお勧めします。
一方、自営業者が加入している国民健康保険は世帯の総所得が基準となっており、総所得には譲渡所得も含まれます。そのため、場合によっては翌年の保険料が一時的に上がる可能性があります。もっとも、譲渡益がない場合や、譲渡益はあるが特例適用により譲渡所得は発生しない場合、譲渡益がわずかである場合は、保険料が上がらないこともあります。
なお、原則75歳以上の高齢者が加入する後期高齢者医療制度についても、国民健康保険と同様に総所得額が保険料のベースとなります。そのため翌年の保険料額に影響が出る可能性があります。
○小規模宅地の特例について
亡くなった人の自宅の土地について「小規模宅地の特例」を使おうとする場合には、相続税の申告期限(亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月)まで居住を継続する必要があり、それまでにその土地を売却してしまうと「80%の評価額の減額」が使えなくなるので注意が必要です。
「小規模宅地の特例」とは、相続税の算定にあたって、土地の評価額を最大で80%減額するもので、実際にこの特例を使ったおかげで相続税がゼロになったというケースが良くあります。なお、配偶者がその土地を相続する場合には、いつ売却しても「80%の減額」ができることになっているので心配ありません。
この制度の適用を受けるにはその他にも様々な要件を満たす必要がありますので、必ず専門家に確認してください。