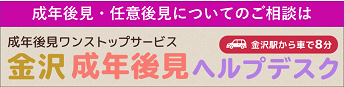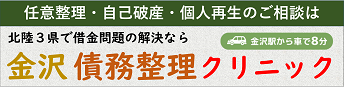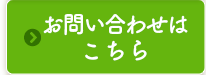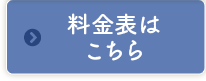遺言書の有無の確認
○遺言書の有無の確認方法
相続が発生した際には、亡くなった人(被相続人)が生前に遺言をしていたかどうかによって、遺産相続の方法や手順が大きく異なってきます。そのため、まずは被相続人の遺言書の有無を確認する必要があります。
被相続人が生前に遺言書の原本やその写しを誰かに預けていたり、保管場所を告げていたりした場合は、その遺言書を探し出して内容を確認すればいいのですが、遺言をしていたかどうかが明らかでない場合や、遺言をしたこと自体は相続人等に告げていたものの、その保管場所が明らかではない場合は、遺言書の有無を確認したり、保管場所を見つけ出す必要があります。これは、遺言書の種類によって方法が異なります。
1.公正証書遺言の場合
公正証書遺言の場合は、遺言者(遺言をした人)が公証人に遺言書を作成してもらった際に、その原本が公証役場で保管されます。また、その際には、遺言者や遺言執行者(遺言書の内容を実現する人)に対して、遺言書の写し(正本や謄本)が発行されます。そのため、遺言者の相続人や受遺者(遺言によって財産をもらい受ける人)、遺言執行者がこの遺言書の正本などを保管していれば、遺言者の死後に、その遺言書正本と遺言者が死亡したことが記載された戸籍謄本等を使用して、遺言者の不動産の名義変更(相続登記や遺贈の登記)をしたり、預貯金の口座解約や払い戻しをしたりすることができます。
また、遺言者が生前には遺言書の内容を知られたくないなどの理由により、相続人や受遺者に対して遺言書の正本や謄本を渡していない場合や、渡していたが相続人や受遺者の側でそれらを紛失してしまったような場合でも、遺言書の原本は遺言者が遺言をした公証役場に保管されているため、その公証役場に請求すれば、正本や謄本は再発行を受けることができます。ただし、再発行を請求することができるのは、遺言者の生存中は遺言者本人(もしくは遺言者の委任状を持った代理人)のみ、遺言者の死亡後は相続人や受遺者などの利害関係人(もしくはその委任状を持った代理人)や遺言執行者に限られます。
なお、被相続人が公正証書遺言をしたことはわかっているが、どこの公証役場で遺言をしたのかがわからない場合や、被相続人の公正証書遺言の正本や謄本を保管しているが、それが唯一の遺言かどうかがわからない場合、そもそも被相続人が公正証書遺言をしたのかどうかもわからない場合は、最寄りの公証役場に必要書類(遺言者が死亡したことが記載された戸籍謄本や遺言者と相続人との続柄のわかる戸籍謄本、請求者の身分証明書や印鑑等)を持参して所定の手続きをすれば、その公証役場から日本公証人連合会が管理する遺言検索システムにアクセスして、全国の公証役場を対象に、その被相続人の公正証書遺言の原本を保管しているかどうか、保管している場合はどこの公証役場に保管しているかを調べてもらうことができます(ただし、昭和64年1月1日以降に作成された公正証書遺言が対象です)。
ただし、この遺言検索システムを利用して、公正証書遺言の原本を保管している公証役場が判明した場合であっても、その遺言書の正本や謄本の交付を請求することができるのは、保管先の公証役場に限られます。つまり、遺言書の「検索」は全国どこの公証役場でも可能ですが、「正本や謄本の交付申請」は、遺言書の原本を保管している公証役場に限られるということです。
2.自筆証書遺言(遺言書保管制度を利用)の場合
2020年7月10日から、全国にある遺言書保管所(法務局)で、自筆証書遺言を保管してもらえる制度が始まりました。この制度を利用して保管された自筆証書遺言であれば、遺言者の死亡後は誰でも、全国の遺言書保管所で「遺言書保管事実証明書」の交付を受けることで、被相続人の遺言書の保管の有無や、保管されている場合はその保管先と遺言者の住所氏名、遺言書の作成年月日などを知ることができます。
また、遺言者の相続人や受遺者、遺言執行者等は、遺言書保管所に対して遺言書の原本の閲覧や、自筆証書遺言の内容を公的に証明する書類である「遺言書情報証明書」の交付を請求することができます。なお、遺言書の原本を閲覧する場合は、その遺言書の原本を保管している遺言書保管所に行かないとできませんが、「遺言書情報証明書」の交付請求は、全国どこの遺言書保管所でもすることができます。つまり、こちらは遺言書の「検索」も「証明書の交付申請」も、全国の遺言書保管所で可能ということです。
さらに、ある相続人等が遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の発行申請を行った場合には、遺言書のそのほかの相続人や受遺者、遺言執行者に対しても、法務局から遺言書を保管している旨の通知がなされます。
なお、通常、自筆証書遺言は、遺言者の死亡後に、管轄の家庭裁判所で「検認」をいう手続きをしておかないと、その遺言書を利用して不動産の名義変更(相続登記)をしたり、預貯金の口座解約や払い戻しを受けたりすることができませんが、遺言書保管制度を利用して保管されていた自筆証書遺言については、遺言者の死亡後に遺言書保管所で発行された「遺言書情報証明書」を利用すれば、「検認」を受けることなく、これらの手続きを行うことができます。
3.自筆証書遺言(遺言書保管制度を利用せず)の場合
上記の遺言書保管制度を利用していない自筆証書遺言については、公的なシステムを使用して遺言書の有無や保管場所を検索するということができません。そのため、原始的な方法ですが、神棚や仏壇の下、金庫や机の引き出しの中など、被相続人の家の中を探すという方法になります。
また、被相続人が遺言書を自宅内に保管しているとは限りません。例えば、相続人のうちの一人や受遺者に預けていたり、顧問弁護士や税理士に預けているということも考えられます。もっとも、そのような場合、遺言書を保管している人は、遺言者が死亡したことを知れば、遺言書を保管していることを名乗り出ることが多いと思われますので、それを待てばいいということになります。もっとも、遺言書を保管している人が遺言者よりも先に死亡していたり、遺言者の死亡時点で認知症になっていたりすることもあり得ますが、そうなると、相続人等が遺言者の遺言書を見つけ出す確率は相当低くなり、場合によっては見つからないまま埋もれてしまうこともあり得ます。
そうなると、遺言書が本当は存在するのに、なかなか発見されず、発見されたときはすでに遺産分割が終わっていた、というケースも起こりえます。遺言により相続人に変更が生じる場合(認知、廃除や廃除の取消が遺言に記載されていた場合)や、遺言の中で相続人以外の者に対して遺贈がなされている場合には、すでになされた遺産分割が無効となります。また、それ以外にも遺言に相続分の指定や遺産分割方法の指定があれば、遺産分割のやり直しが必要となる場合があります。
そのため、これから遺言書を作成しようとしている方は、公正証書遺言にするか、自筆証書遺言なら遺言書保管制度を利用するか、または何らかの工夫をすることによって、自分が死亡した後で遺言書を発見してもらえるようにする方法を、よく検討する必要があると思います。
なお、遺言書保管制度を利用していない自筆証書遺言については、管轄の家庭裁判所で「検認」をいう手続きをしておかないと、その遺言書を利用して不動産の名義変更(相続登記)をしたり、預貯金の口座解約や払い戻しを受けたりすることができません。
○遺言書が2通以上見つかったら
遺言は、作成した本人が生きているうち(遺言能力があるうち)は、何度でも作成し直すことができます。そして、本人の死後に、内容の矛盾する遺言が複数発見された場合には、最も新しい(死亡日に近い)遺言が優先します。そのため、被相続人の遺言書やその写しが手元にある場合であっても、その遺言書が最も新しいものかどうかについては、念のため確認する必要があります。
民法では、「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。」と定めています。したがって、例えば、前の遺言では「自宅は長男に相続させる」旨が書かれていて、後の遺言では「自宅は二男に相続させる」旨が書かれている場合には、双方の遺言の内容は明らかに両立しないので、後の遺言によって前の遺言は撤回されたことになり、自宅は二男が相続することになります。
なお、遺言書には日付は必ず記載されているはず(作成日付のない遺言は無効)ですが、封印された自筆証書遺言で封筒に作成日付が書いていない場合には、検認までは開封することはできないので、見つかった遺言書はすべて家庭裁判所に持ち込むことになります。
○遺言書の検認
遺言書保管制度を利用していない自筆証書遺言については、前述のとおり、遺言者の死亡後に管轄の家庭裁判所で「検認(けんにん)」という手続を受ける必要があります。検認とは、家庭裁判所で、裁判所の職員と相続人らが立ち会って遺言書を開封し、遺言書の状態や内容を確認して、検認後に遺言書が破棄されたり改ざんされたりすることを防ぐための手続です。したがって、その遺言書が法的に有効かどうかを判断する手続ではないのですが、検認を受けておかないと、その遺言書を利用して不動産の名義変更(相続登記)をしたり、預貯金の口座解約や払い戻しを受けたりすることができません。家庭裁判所に検認を申し立ててから検認期日までは1か月位の期間がありますが、その間はこれらの手続ができないことになります。
検認の申し立ては、遺言書の保管者や遺言書を発見した相続人が、遺言者の死亡を知った後、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に対して、遅滞なく行う必要があります。その際には収入印紙を貼った検認の申立書のほか、遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本や、相続人全員の戸籍謄本など、遺言者の相続人を特定するために必要なすべての戸籍謄本等の提出が必要となります。
検認の申し立てがなされると、相続人に対し、家庭裁判所から検認期日(検認を行う日)の通知が送られてきます。申立人は印鑑や遺言書の原本を持参して参加する必要がありますが、申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは各人の判断に任されており、全員がそろわなくても検認手続は行われます。
検認期日では、申立人から提出された遺言書を、出席した相続人等の立会のもとで、裁判官が検認します。なお、封印された遺言書は、検認前に勝手に開封してはなりません。これに違反すると5万円以下の過料に処せられます。遺言書の検認自体を怠った場合も同様です。ただし、これらの場合でも、遺言書自体が無効になるわけではありません。
検認が終わった後は、遺言の執行をするために、検認済証明書の申請(遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要となります。)をすることになります。
なお、公正証書遺言や、遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言については、家庭裁判所で検認を受ける必要はありません。そのため、公正証書遺言の正本や遺言書情報証明書を使用して、不動産の名義変更(相続登記)をしたり、預貯金の口座解約や払い戻しを受けたりすることができます。