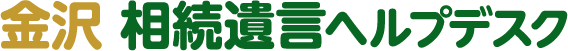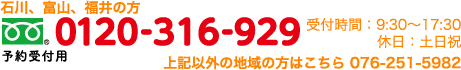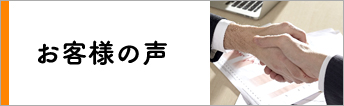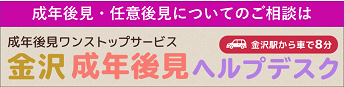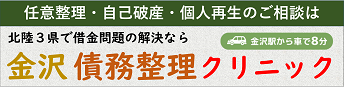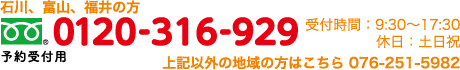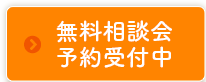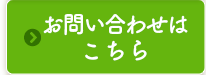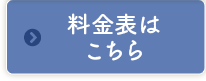遺産分割協議の注意点
○遺産分割協議の注意点
1.遺産分割協議の注意点
遺産分割協議を行う場合、いくつか注意しなければならない点があります。
■必ず相続人全員で行います。ただし、必ずしも一堂に会して話し合う必要はなく、全員が合意している内容の協議書を、郵送などの持ち回りで署名・押印する、という形をとっても良いです 。
■「誰が」「どの財産を」「どれだけ取得するか」を明確に取り決め、遺産分割協議書に記載します。
■合意できるのであれば、後日発見された遺産を、どのように分配するかも決めておきます。
(記載漏れがあっても、改めて協議書を作成しなくて済むため)。
■形見分けは自由にできます(形見分けとは、故人の愛用の衣類や時計等、身の回りの物を分けること)。
ただし、相続放棄や限定承認を希望する場合、形見分けの品が特に高額な場合には、単純承認とみなされる場合もあるので注意が必要です。
■相続人の一人が遺産分割前に自分の法定相続分を処分した場合には、その法定相続分を譲り受けた人を、必ず遺産分割協議に参加させなければなりません。
■相続人の一人が無断で遺産を処分してしまった場合には、他の相続人は、勝手に処分した相続人に対して、自分たちの相続分を返却するよう請求できます。その相続人が請求に応じない場合には、相続回復を請求する調停や審判を家庭裁判所に申し立てる事ができます。
ただし、処分した財産が動産の場合、取得した第三者が何も事情を知らなかった場合には、返還を請求できなくなる場合があります(即時取得)。
2.遺産分割協議のやり直し
遺産分割協議は、原則として一度成立すると、もう一度やり直すことはできません。
ただし、下記のようなケースであれば、一部または全面的にやり直すことができます。
■遺産分割の際に、相続人の意思表示に詐欺・強迫・錯誤などがあった場合
遺産分割協議の際に、相続人が他の相続人に騙され、あるいは脅され、または勘違いをして合意をした場合(例)相続人が他の相続人に「故人には財産はない」などと騙されていた場合
■遺産分割後に、遺産分割時の前提条件が変更された場合
発見された遺産が重要で、その遺産があることを知っていれば、このような分割協議はなされなかったであろうと考えられる場合(例)被相続人が高額の特許権や著作権を有していたことが、後日判明した場合
■相続人全員が合意した場合
相続人全員が、すでに成立している遺産分割協議の全部、一部を合意により解除した上、改めて遺産分割協議を行うことも可能です。(ただし、税務上は相続人同士での贈与とみなされる危険性があります)
○このような相続人がいたらどうする?
相続人を調査していると、相続人の中に下記のような人たちが含まれている事例も少なくありません。しかし、遺産分割協議は相続人全員で行わなければならないため、下記のような人たちを除外して行われた遺産分割は無効となります。そのため、このような場合には専門家に相談して、きちんと法的な手順を踏んで手続きを進めることが必要です。
また、自分が亡くなったら相続人になる人(推定相続人といいます)に中に下記のような人たちが含まれている場合には、推定相続人たちに余計な苦労をかけないためにも、まだ元気なうちに遺言をしておくことをお勧めします。
1.相続人に認知症の人が含まれる場合
 認知症の程度にもよりますが、判断能力が常に全くない場合には、遺産分割協議をする前に、その相続人のために家庭裁判所で成年後見人の選任申し立てを行います、そして、選任された成年後見人がその相続人を代理して、遺産分割協議を行うことになります。
認知症の程度にもよりますが、判断能力が常に全くない場合には、遺産分割協議をする前に、その相続人のために家庭裁判所で成年後見人の選任申し立てを行います、そして、選任された成年後見人がその相続人を代理して、遺産分割協議を行うことになります。
ただし、成年後見人自身も相続人となっている場合には、その相続人のために、家庭裁判所で特別代理人を選任してもらう必要があります。
2.相続人に未成年者が含まれる場合
 未成年者は、単独で有効に法律行為をなし得る能力(行為能力)が制限されているため、遺産分割協議に参加することができません。そのため、その未成年者の親権者が法定代理人となりますが、親権者自身も相続人となっている場合には、その未成年者のために、家庭裁判所で特別代理人を選任してもらう必要があります(未成年者が二人以上いるときには、それぞれの子のために別々の特別代理人を選任してもらう必要があります)。
未成年者は、単独で有効に法律行為をなし得る能力(行為能力)が制限されているため、遺産分割協議に参加することができません。そのため、その未成年者の親権者が法定代理人となりますが、親権者自身も相続人となっている場合には、その未成年者のために、家庭裁判所で特別代理人を選任してもらう必要があります(未成年者が二人以上いるときには、それぞれの子のために別々の特別代理人を選任してもらう必要があります)。
3.相続人に行方不明の人が含まれる場合
 行方不明の相続人が一定の調査をしても見つからない場合には、その人の財産を管理する人(不在者財産管理人)を家庭裁判所に選任してもらい、代わりに遺産分割協議に参加してもらうことができます(事前に家庭裁判所から権限外行為の許可をとる必要があります)。
行方不明の相続人が一定の調査をしても見つからない場合には、その人の財産を管理する人(不在者財産管理人)を家庭裁判所に選任してもらい、代わりに遺産分割協議に参加してもらうことができます(事前に家庭裁判所から権限外行為の許可をとる必要があります)。
また、行方不明の状態が一定期間続いていたり、災害や事故などで行方不明になったりした場合には、家庭裁判所に失踪宣告の申し立てをして、その人が亡くなったものとして手続きを進めることもできます。
4.被相続人に、前妻(前夫)との間に生まれた子や、婚外子がいる場合
 例えば、亡くなった人(被相続人)に前妻との間に生まれた子と、再婚後の妻がいる場合、相続人はこの子と後妻となり、法定相続分は2分の1ずつとなります。
例えば、亡くなった人(被相続人)に前妻との間に生まれた子と、再婚後の妻がいる場合、相続人はこの子と後妻となり、法定相続分は2分の1ずつとなります。
また、婚外子(法律上は非嫡出子といいます)も、被相続人から認知されていれば相続人となります。非嫡出子の法定相続分は、従来は法律上の夫婦の間に生まれた子(嫡出子)の半分となっていましたが、現在では嫡出子と同じ割合になっています。