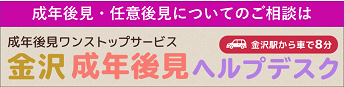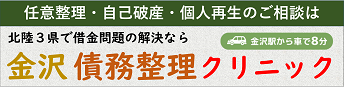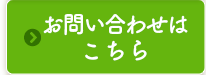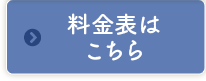負担付死因贈与契約とは
贈与する人と、贈与を受ける人との合意内容を契約で交わすのが死因贈与契約です。
贈与する方の意向を、贈与を受ける方は合意しているとみなされますので、贈与した方が亡くなった後、一方的に放棄することが出来ないのが特徴です。
これに対して、遺贈は、遺言者の単独行為であり、受遺者は、遺言者の死亡後にいつでもこれを放棄することができますし、遺言書に分割方法の指定が記載されていても、執行者がいなければ、共同相続人、受遺者全員の合意により、遺言内容と異なる遺産分割協議をすることは可能です。
また、遺言執行者が選任されており、その同意を得ないでされた遺産分割協議であっても、遺贈を受けた相続人が、遺言の内容を知りながら遺産分割協議に参加した場合などは、相続人全員で遺言と異なる遺産分割協議をすることも可能と解されています。
したがって、もし、ある財産を特定の人に贈与する意思を確実に実現したい場合には、死因贈与契約も有効と言えます。
さらに「負担付」というのは、贈与をする方が、贈与を受ける方に、何らかの義務・負担を強いることです。
遺贈の場合には生前の受贈者の負担というのはありませんが、負担付死因贈与の場合には、贈与を受けた方は、相続が発生するまで、その義務・負担を全うし、利益を受けるということになります。
具体的には、“今後の身の回りの世話を続けて欲しい”“同居して面倒を見て欲しい”といったケースが多く、遺言書よりも実行度合が強く、成年後見よりも自由度が高いという意味で、使い勝手の良い制度になっています。
負担付死因贈与契約の注意点
死因贈与の手続きにおいて、注意をしなければならないのは、契約内容の実行に疑問が発生したり、相続人間でトラブルが出ないようにしておくことです。
契約内容を明確に記載しておくことが大切で、
■贈与の対象資産
■負担の内容
が特に重要です。
資産が不動産の場合は、登記事項証明書の記載に従って正確に記載しましょう。
また、預貯金は「銀行名」「口座の種類・番号・名義人」を明示します。
死因贈与契約も遺言書と同様に、執行者を指名することが可能です。
通常、死因贈与契約の内容は、他の相続人と利害が対立することが多いため、弁護士や司法書士、行政書士などの専門家を指定しておけば、執行が確実に進められることでしょう。
負担付死因贈与契約に、公正証書を利用する
死因贈与契約というのは、一般的な贈与契約と同じ類のものであり、書面になっていないと、贈与をする方が撤回することが可能であるとも考えられます。
贈与を受ける場合、負担をするわけですから、撤回されないために書面にしておくことが大切です。
負担付死因贈与契約書には公正証書を利用するのが、最も安全と言えるでしょう。
負担付死因贈与契約の取り消し
負担付死因贈与の取り消しについては、その負担が履行されたかどうかで、大きく違ってきます。
まず、負担が履行されていない場合、遺贈の取り消しの規定により、取り消すことが可能です。
また、負担のない死因贈与契約の場合は、これもいつでも取り消すことが可能です。
(*ただし、書面で贈与契約が行われた場合には、取消できないとの学説もあるそうです。)
しかし、負担が全部または一部履行された場合は、原則として取り消すことができません。
ただし、取り消すことがやむをえない「特段の事情」があれば、遺贈の規定により取り消すことができます。
死因贈与契約の特徴を端的に整理すると、
◇贈与を受ける人の承諾が必要
◇負担を条件とすることで生前に負担を履行させることができる
◇原則として受贈者が放棄することはできない
となります。
また、贈与を受ける人にとっても、死因贈与にはメリットがあります。
不動産を贈与の目的とした場合、遺贈では遺贈者の生前に登記をすることはできませんが、死因贈与では、贈与者の生前においても受贈者に対して「所有権移転仮登記」をすることができます。
これによっても、死因贈与の取消を完全に防ぐ効力があるわけではありませんが、仮登記には順位を保全する効力がありますので、この仮登記の存在によって、贈与者が目的不動産を売却しようとしても、買い手が見つかりにくくなったり、抵当権を設定して借入をしようとしても金融機関が融資を断るなど、事実上、仮登記に抵触した行為をしにくくなると考えられます。
遺贈と死因贈与はいずれも、贈与する方が亡くなったときに効力が発生しますが、遺言による遺贈が厳格な形式が要求され、形式に不備がある場合には遺贈が無効となることも考えられます。
それに対して、死因贈与は両者の合意があれば、遺言のような厳格な形式は要求されておらず、より確実にご自身の意思を実現することができます。
また、負担付遺贈では、生前に受贈者に負担を負わせることができないのに対し、負担付死因贈与契約では、生前に負担を受贈者に負わせることができる点にも実効性があります。
ただし、遺言書と同じように、遺留分減殺請求の行使は受ける可能性があります。
遺留分を考慮した設計が必要となるでしょう。